目次
ピアノの「練習嫌い」を作るのは「時間と回数」。
今回はピアノの練習についてお話をしたいと思います。よく「昔、ピアノを習っていたんだけど練習が嫌いで辞めちゃった」をよく聞きます。実は私も「練習嫌い」のひとりでした。今考えると「練習」という言葉の本当の意味を理解していなかったんだと思います。
小さい子なら回数や時間でも仕方ないが、練習の本当の意味は?
私も小さい子供(幼稚園児など)の生徒に対しては、「練習→回数をやること」と指導しています。なぜなら幼児の場合「出来るようになるためには回数をこなす」という経験がない場合もあるので、とにかく「回数をやる」→「できないことができるようになる」という仕組みを脳にインプットしてあげなければいけません。正直、回数は5回やろうが、10回やろうが「その回数に意味はなく」、ピアノの前に座っていられることと回数をやることで「出来るようになった!」という経験をしてもらいたいのです。
練習を時間や回数を目的にすると「練習嫌い」を作ってしまう?
また私が子供だった頃、先生たちは「毎日、最低30分とか最低1時間」とか、時間で練習のことを表現していました。
もしかしたら、今思えば・・・なのですが、大人になっても「ただ30分回数をやるためにピアノに向かう」ということを練習だと思っていたのかもしれません。でも、それでは練習嫌いを作ってしまう可能性も高いです。というのは、回数としてしまうと「その回数ができない→いけないこと」になってしまったり、「その決められた時間が出来ない→いけないこと」になってしまうので、練習が出来なかった場合など、「いけない自分」を自分の中に抱え込んでしまって、どんどん自分の中にストレスを溜め込んでしまうのです。そして「練習が嫌いになる」という仕組み。
「練習してきてね!」の言葉は生徒をどんどん追い込んでいるという事実
私の教室の生徒さんには「練習してきてね」という言葉は、小学生以上の生徒には使いません。(この言葉を使うとしたら幼稚園児か保育園児です。)それ以上の生徒、小学生、中学生から大人まで「練習してきてね」の言葉の代わりに使う言葉は「研究してきてね」という言葉です。
実は、私も最初からこの言葉を使っていたわけではありません。教えはじめたばかりの頃は「練習してきてね」と言ってきたし、練習してこない生徒に対しては「なんで練習してこないんだろう?」って不思議に思っていました。
というのは、「ピアノを習う→練習すべき」という図式が固定概念として私の意識の中にあったからです。でも、よく考えてみたら、これってエゴなんですよね。ピアノを習う→練習の方法がわからないという生徒もいる場合もあるのです。
じゃぁ、「練習ほの方法ってなに?」と考えた場合、(当時の)私の脳の中には「時間(30分はやるとか)と回数(10回はやる)」で相手を拘束することしか思いつきませんでした。ところが、これじゃぁ、相手はイヤになってしまうんですよね。
どういうことかというと、私の先生は私に対して「ピアノを教えているんだから、これくらいやらないとね」とたまにそんなことをおっしゃいます。この言葉って裏を返せば「先生のくせに、こんなこともやらないの?」という意味にも取れるわけで、それが出来ない自分→ダメな自分→「課題ができていないから、行くの嫌だな・・」という流れになってしまう場合もあるのです。
これは、決して私が(私の)先生に対する悪口を言っているわけではないのです。先生もそのつもりはないと思いますし、愛情で言ってくださっているというのも十分に理解していますので(どうでもよい人間に対しては言わないという法則)。でも、これを自分と生徒の関係で考えると、「なるほど・・そういうことか!」ということに気づきました。
私は知らないうちに生徒を追い込んでいたのかも???と。
「練習してきてね」ではなく、「研究してきてね!」という宿題。
「練習してきてね!」という言葉が生徒を追い込んでいるのかも?ということに気づいた私は、「研究してきてね」という言葉を見つけることができました。
「研究してきてね」というのは、何かの課題があった時に、まず「何かの仮説を立て」てそれが「出来るようになるのか?」「出来るようにならないのか?」ということを検証します。練習ではなく「検証」、つまり「やってみて試す」ということを繰り返すのです。1週間経過して出来るようになれば、それは「その生徒にとって正しい行動」。全然効果がなければ「やっても仕方がない行動」という結果を導き出すことができます。
この検証は、生徒それそれで回答が変わってきます。なぜなら生徒一人一人に個性があり、理解力はもちろんですが指の長さ、骨格、家庭環境、ピアノに対するモチベーション、性格などいろいろな条件が伴うからです。なので、私は「あなたに合ったやり方を見つけてね」とサポートします。
つまり、誰にでも通用するような正解はないのです。正解は、その生徒が「正解と思ったこと」が正解なのです。その正解は「時期によっても異なり」ます。1年前の正解と1年後の正解は違って良いのです。なぜなら、1年前のその人と1年後のその人は違う人間だから。
もし、練習で行き詰っている方がいらっしゃったら、もしくは先生の立場で「なんで生徒が練習してこないんだろう?」と思っていらっしゃる先生がいたとして、この記事がその方のお役に立ったら嬉しいです。
・・・・・・
幸せピアノ・メールマガジンやっています。
「幸せピアノ」メールマガジンのご案内。美しい音、幸せマインドetc….
・・・・・・
こちらの記事もお役に立つかも??
・・・・・・・
あなたがピアノで幸せになるのを応援しています。
今日も訪れていただきありがとうございます。
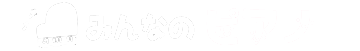






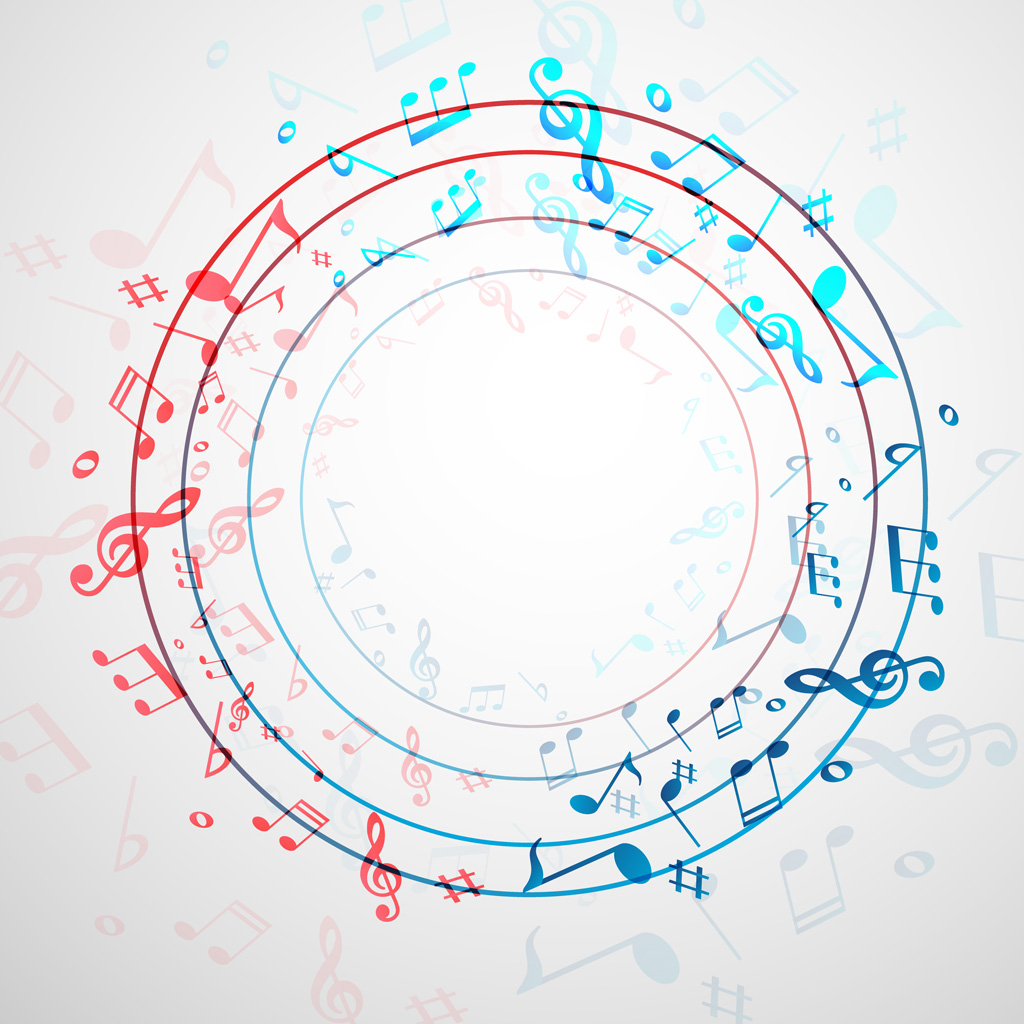

















コメントを残す